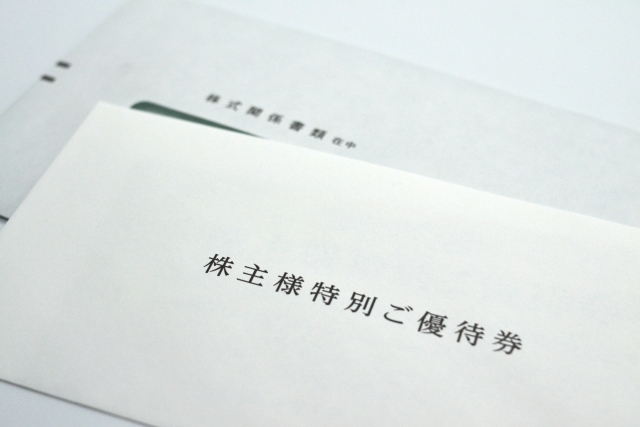資金20万円から始める投資!
仮想通貨もいいけど、王道の株式投資がもっと良いワケ
|PR|2018年5月|岡三オンライン証券株式会社
昨年度末をピークにして、巷で話題になった仮想通貨。
最高値付近では1億円以上の投資利益を手にした「億り人」なる人たちも多く誕生し、すわ「投資のトレンドになる!」とささやかれました。しかし、この仮想通貨での資産運用の裏に隠された落とし穴に気づいている人は案外多くはありません。
その落とし穴とは、税率です。実は仮想通貨は税制面で見ると、数ある投資の中でも決して優位に立つ投資手法ではないことがわかってきます。では、税制面でも優位に立てる投資とは何か。
今回は「税金で泣きを見ない投資」をご紹介していきます。
知らないと損する!? 仮想通貨と株式投資、税制がこんなに違う!

いきなりですがクイズです。
年収500万円の会社員Aさんが仮想通貨に投資しました。仮想通貨は驚くほどの高値をつけ、Aさんは5,000万円の利益を確定させることができました。
しかし、翌年の確定申告で驚くべき事実を知らされました。
「えっ、こんなに税金取られるの!?」。
Aさんが腰を抜かした、納税額はどれほどのものだったでしょうか?
まずはヒントを。
仮想通貨の利益は、雑所得に入ります。
ということは、所得と合算するため5500万円の場合、所得税率が45%。住民税10%となるわけですね。
そうです、答えは仮想通貨で得た利益の約55%、つまり約2,750万円が税金だったのです!
仮想通貨といえば、久々のバブリーな話で夢があると思いきや、この税率はなんとも悲しくなってしまいませんか。 もちろん本記事は読者のみなさんの夢を壊すために書いているのではありません。
仮想通貨に夢はなくとも、ちゃんと夢のある投資方法が世の中にはあるのです。それが株式投資です。 実は長く投資を続けている人からすると、株式投資ほどメリットが多いものはなく、まさに資産運用の王様と呼ぶにふさわしいもの。
さっそく懸念の税制面で仮想通貨と株式投資を比較してみましょう。

先ほどの通り仮想通貨の利益は雑所得に入ります。
これはわかりやすく言うと、手にした所得の総額を求め(給与所得や他所得を合算させた総所得)、その所得額に準じて税率が決まるというもの。
つまり、儲かれば儲かるほど高い税金になっていくのです(最高税率は所得税45%+住民税10%の55%)。
一方、株式投資の利益は申告分離課税という方式が採用されており、利益に対して一律で20.315%の税金がかかるだけ。
つまり、100万円だろうが5,000万円だろうが1億円だろうが、税率が変わらないのです!
これは銀行預金の利息の課税(20.315%)と同じ。国からも優遇されているのがよくわかります。
理解すると面白くなる「株式投資」

なるほど、株式投資は仮想通貨よりも税制面で優遇されているのでしょうが、そもそも儲かるものなのでしょうか?
株式投資とは、企業が発行した「株式」を売買する投資方法です。
買った株式の株価が上昇することにより「値上り益(キャピタルゲイン)」「配当金(インカムゲイン)」を手にすることができるのが最大のメリット。
また株式を購入(=所有)することによって、その企業の株主になるので株主優待サービスなどを受けることもできるようになります。ほかにも、インフレに強い抗インフレ効果に注目して株式投資を選ぶ人も少なくありません。

もちろん株式投資にはリスクもあります。所有している企業の業績がぱっとせず、株式の価値が下がれば「値下り損(キャピタルロス)」になったりしますし、企業が倒産したりしてしまう可能性もなくはありません。
しかし、こうしたメリット・デメリットは、さまざまな内的・外的要因によって左右されるので、なぜ株価が上昇したのか、なぜ下落したのかの原因を分析することができます。
つまりまったく根拠のない値動きをしないので、人為的にリスクコントロールをすることも不可能ではないのです。
ところが仮想通貨は、この根拠が乏しく、純粋に需給によってのみ価格変動が引き起こされています。つまり「みんなが買っているから値が上がっている」という、ただそれだけの根拠しかないのです。
どのように売買が進んでいるか、実態を完全に把握するのも難しいので、内的・外的要因を客観的に見ることが大変難しいのです。
こうした点からも、仮想通貨と株式投資の扱いやすさが大きく異なるのがわかりますね。
あの有名企業は150万円が4億円に!? 株式投資の醍醐味とは?

もっとも株式投資も「投資」ですから、保有する株式の値が上がったり、多くの配当金がもらえなければ投資している意味がありません。では、どのような銘柄で、どのくらいのリターンがあったのか、具体例を見て検証しましょう。

日経225採用銘柄のうち、過去10年間で見てみると、圧倒的なのはSUBARU。なんと590%超えを誇っています。
ユニクロでお馴染みのファーストリテイリングは約480%、ソフトバンクも約475%とかなりの上昇率ですね。

また、見逃せない銘柄はたくさん。まずはヤフーとセブンイレブン。
ヤフーは、1997年一部上場当時の安値が約150万円。株式分割をした結果、約4億400万円の儲けを手に!(2018年3月29日現在)
セブンイレブンを経営するセブン&アイ・ホールディングスも同様、1979年当時の株価1,800円は現在4,532円(2018年3月29日)の株価になり、元手180万円が1億7,200円に大化け!

億万長者とはまさにこのことですね。 ここに加えて配当金も出てきますから、企業が成長すればするほど儲かるわけですね。
さらに、短期的に成長した銘柄も。
ニトリは、5年前2012年12月28日終値3,165円から18,485円に(2018年3月29日現在)。なんと5.8倍!
今やTVCMでも話題の「MonotaRO(モノタロウ)」は2012年年12月28日終値694.5円から3,730円(2018年3月29日現在)。こちらも約5.4倍。しかもただ儲かるのではなく、株主になるということは応援したい企業のオーナーになるわけですから、自分の応援(投資)をもとに企業が成長する姿を見ると、感慨もひとしおです。
仮想通貨にはこのような成長応援メリットはありませんし、比較検討する要素もほとんどないので、株式投資のほうがより投資を楽しむことができると言えます。
しかし「株式の購入って敷居が高いイメージがある」という声が多いのが悲しいところ。
実は20万円以下でも株式購入は可能で、20万円以下で購入できる東証銘柄は全市場銘柄の約61%もあるんです!(2018年3月19日)
さらに言えば、優待銘柄はそのうち25%にあたる661銘柄もあるんです!
この事実を知るだけでテンションがあがってしまいますね。しかも、全国の証券取引所では、株式の売買単位を100株へ統一する動きになってきているので、昔より購入しやすい株式が増えているのです。
少額で始めるならオススメは岡三オンライン証券

実際、株式投資を始めるうえで、どの証券会社を選べばいいか、迷ってしまうことも少なくありません。
そんなときはまず手数料はリーズナブルで、情報収集能力がしっかりしている証券会社を選ぶようにしましょう。
「情報の岡三」と業界で言われるほど多くの投資情報を持っている岡三オンライン証券では、現物取引および信用取引において20万円以下の手数料が0円と投資家に優しい環境です。
また2017年「みんなの株式」ネット証券ランキング取引ツール1位に選ばれるなど、取引ツールが充実しているので、株式投資を始めたばかりの人も使いやすいのが特長です。
少額から株式投資を始めるならば、いろんなキャンペーンを開催している岡三オンライン証券はうってつけと言えます。
仮想通貨のバブリー感に魅了される気持ちもわからなくはないですが、手軽に始められる「株」の魅力のほうが何倍も高いのではないでしょうか。
岡三オンライン証券
詳しくはこちら >>https://www.okasan
【定額プラン】20万円以下の取引手数料0円はこちら
商号等 岡三オンライン証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第52号加入協会 日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会 ・投資信託取引のリスク ▼価格変動リスク 投資信託は、国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対象とするため、当該資産の市場における取引価格の変動や為替の変動等により基準価額が変動します。これにより投資元本が割り込み、損失を被る場合があります。▼為替変動リスク 外貨建て資産に投資する投資信託は外国為替相場の変動などにより、円換算でのお受取金額が減少するおそれがあります。これにより円換算で投資元本を割り込み、損失を被る場合があります。▼信用リスク 組み入れた株式、債券および商品等の発行者の倒産等、発行会社の財務状態の悪化或いはそれらに関する外部評価の変化等により基準価額が下落することがあります。これにより投資元本を割り込み、損失を被る場合があります。▼流動性リスク 有価証券の時価総額が小さくまたは取引量が少ないとき、市況が急変したとき、取引所が閉鎖されたときには、有価証券の売買価格が通常よりも著しく不利な価格となることや有価証券の売却ができなくなる場合があります。このような場合には、当ファンドの基準価額が下落し、損失を被る可能性があります。▼カントリーリスク 外国の外貨不足などの経済的要因、外国政府の資産凍結などの政治的理由、外国の社会情勢の混乱等の影響で、当ファンドの基準価額が下落し、損失を被る可能性があります。特に、エマージング諸国は、主要先進国と比較して、経済・政治・社会情勢等で脆弱または不安定な側面があることから、エマージング諸国のカントリーリスクは主要先進国に比べ高くなる傾向にあります。手数料等諸費用の概要(表示は全て税込・上限金額):【日本株】取引手数料には1注文の約定代金に応じたワンショットと1日の合計約定代金に応じた定額プランがあります。ワンショットの上限手数料は現物取引で3,240円、信用取引で1,296円。定額プランの手数料は現物取引の場合、約定代金100万円以下で上限864円、以降約定代金100万円ごとに540円加算、また、信用取引の場合、約定代金200万円以下で上限1,080円、以降約定代金100万円ごとに324円加算します。手数料プランは変更可能です。信用取引手数料は月間売買実績により段階的減額があります。信用取引には金利、管理費、権利処理等手数料、品貸料、貸株料の諸費用が必要です。【上場新株予約権証券】日本株に準じます。【中国株】国内取引手数料は約定金額の1.08%(最低手数料5,400円)。この他に香港印紙税、取引所手数料、取引所税、現地決済費用の諸費用が必要です。売買にあたり円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものとします。【外貨建て債券】外貨建て債券を募集・売出し等により、又は当社との相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。外貨建て債券の売買、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものとします。【先物】取引手数料は、通常取引コースの場合、日経225先物が1枚につき324円(取引枚数により段階的減額あり)、日経225mini、ミニTOPIX先物、東証REIT指数先物、TOPIX Core30先物、東証マザーズ指数先物、JPX日経インデックス400先物が1枚につき43円、TOPIX先物、日経平均VI先物が1枚につき324円、NYダウ先物が1枚につき864円。アクティブ先物取引コースの場合、日経225先物が1枚につき270円、日経225miniが1枚につき27円です。【オプション】取引手数料は、日経225オプションが約定代金に対して0.1728%(最低手数料216円)、TOPIXオプションが約定代金に対して0.216%(最低手数料216円)です。【株価指数証拠金取引】取引手数料は、1枚につき153円です。【投資信託】お申込みにあたっては、当該金額に対して最大3.78%の申込手数料をいただきます。換金時には基準価額に対して最大0.75%の信託財産留保金をご負担いただく場合があります。信託財産の純資産総額に対する信託報酬(最大2.484%(年率))、その他の費用を間接的にご負担いただきます。また、運用成績により成功報酬をご負担いただく場合があります。詳細は目論見書でご確認ください。【FX】取引所FXの取引手数料は、くりっく365が無料、くりっく365ラージが1枚につき1,000円です。店頭FXの取引手数料は無料です。スプレッドは、通貨ごとに異なり、為替相場によって変動します。Webサイトで最新のものをご確認ください。
|
会社情報|
Copyright © Okasan Online Securities Co.,Ltd.All Rights Reserved.